



金融ワカラナイ女子による、
ワカラナイ女子のための金融コミュニティ
身近な家計管理から世界経済まで、広い意味での「金融」をテーマに勉強する女子会を開催しています。女子会は、基本少人数制。同世代や同じ目線の方々が、安心して話せる場所になるよう工夫しています。「自分なりの判断基準」を見つけていくお手伝いをしています。

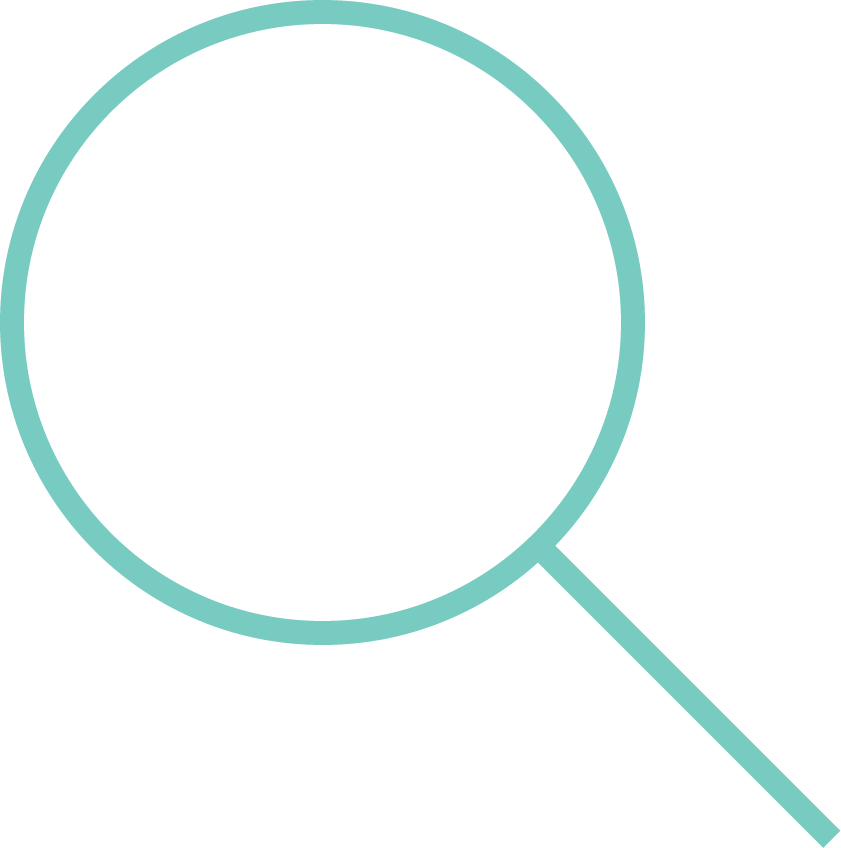

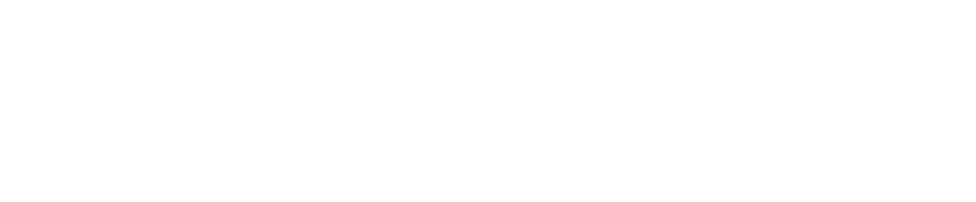
*レポートページに移動します。

コラム
こんにちは!インターン生のななみです♪ 難しくてかたいイメージのある金融について、絵本で勉強しました! 今回は、絵本から金融について学んだことをみなさんに共有したいと思います!
2023.9.5up!
こんにちは!
インターン生のななみです。
突然ですが、私はきんゆう女子。でのインターンで金融と関わってみて気がついたことがあります。
それは、金融は難しいという先入観のせいで、金融を「なんとなく避けている人」が多いということです!
金融は用語に漢字も横文字もあるし、数字も出てくるし、堅実な企業が多いだけに堅苦しいイメージがありますよね。
私もそうでしたが、そのような理由で最初の一歩が踏み出しにくい分野なのかもしれません。
しかし、自分の将来を自分で守れるようになるためにも、お金についての知識は必要不可欠だと思います。
金融について少しでも知っていれば、学びたいという気持ちが湧いてくるかもしれない……
そんな願いを込め、このコラムでは誰もが一度は読んだであろう「絵本」から金融について一緒に学びたいと思います!
まだ金融を学んでいない方も、すでに金融を学んでいる方も、ぜひ最後までご覧ください。
人類が誕生して間もないころ、人々は住むところを転々としながら狩りや食料採集をして、家族単位のグループで生活していました。
しばらく経つとグループ内で物々交換が始まり、自然と他のグループとも物々交換をするようになりました。
氷河期の終わりには、人々は植物を栽培し、動物を飼育し始めました。
すると土地に定住することになるため、良質な土地を持っている一族が多くの作物を収穫したり、羊やヤギを飼えるようになりました。
そして、それらを他の物と交換するとき優位に立ったそうです。
しかし、便利な物々交換にも問題があります。
なぜなら、物々交換は自分が持っているものとしか交換できないからです。
「小麦」を「ヤギ」と交換してほしいのに「ヤギ」は要らないから「小麦」はやれないと言われてしまったら、「ヤギ」しか持っていない人は何もできません。
ああ、自分が持っているものが保管や持ち運びがしやすい便利なもの、例えば「穀物」だったら交換してもらえたのだろうか……
そう思うのであれば、「穀物」と「ヤギ」を交換してくれる人を探して一度「穀物」を手に入れます。
そして、「ヤギ」と交換して得た「穀物」と最初に欲しかった「小麦」を交換することで、自分が欲しいものを手に入れることができました。
こうするとみんながそれぞれほしいものを手に入れられて、一件落着となったんです。
1万年前には、おはじきのようなものが粘土に密閉されている「トークン」が作られました。
これらは、例えば小麦の入った袋が穀物倉庫にいくつあるかを記録するために用いられました。
穀物が必要になった時は包みを割って穀物とトークンの数を照らし合わせていました。
そのうち、人々は周りの粘土にトークンの数だけ丸を付けて外から見えるようにすれば、包みを割らなくても良いと気が付きました。
トークンそのものがなくてもやり取りできるようになったため、次は省略文字や数を表す記号を粘土の板に書くようになりました。
例えば、羊100匹を記録するのに羊の絵を100個描くかわりに、羊1匹と100個を意味する記号を書いていたそうです。
小麦を栽培したり羊を飼育したりするのと同時に、人々は金属の塊を掘り出し始めました。
金や銀は道具として使うには柔らかいため、アクセサリーやお守りとして使われていた。
しかし、時が過ぎて銅やスズ、鉄を大量に採掘できるようになると、高温の火を使って道具や武器を作り始めました。
それでも金や銀、エレクトラムは貴重だったため、主に有力者がそれを所持し、取引に使われていました。
これが、お金の誕生です。
なお、銀は重さで価格が決まっていたため、当時は寺院で重さを計っていました。
また、王などの統治者がお金に関する法や規則を作り、油や布などの値段もその価値を銀で評価していました。
ちなみに、文章や記憶が考え出される前、何かを借りることはやっかいなものでした。
なぜなら、人の記憶はしばらく経つと正確にどれくらい借りたか忘れてしまうからです。
そのため、貸し借りの内容を粘土板に掘って火で焼いた借用書が作られました。
形として残る借用書の誕生は、信頼できる証拠になっていました。
紀元前600年になると、硬貨が世界のあちこちで現れました。
確かに、硬貨の重さが決まっていれば寺院に行って重さを計らなくても価値が分かるため、便利ですよね。
最初はお金持ちの売買用に金や銀、エレクトラ厶が作られていて、そのあと庶民の日用品の売買のために銅や青銅で作られた硬貨が出現しました。
その際、実際に含まれる金属の価値よりも高めの価値をつけることで、国や統治者が儲けを得ていたそうです。
また、同時期に両替商も出現しました。
両替屋は国外の商人から金の塊や硬貨を両替して儲けを上乗せしたり、高い利子をとって人のお金を貸し出したりしていました。
この両替屋から後の銀行家が生まれたと言われています。
だんだんと現代に近づいてきましたね!
紙幣が登場したのは紀元1000年中国です。
当時の中国では銅貨が不足し、皇帝が銅貨での支払いを禁止していました。
そして、その代わりに政府が発行した証明書と銅貨を交換するようにしたことが紙幣の誕生だと言われいます。
やがてヨーロッパの国々も紙幣を発行するようになりましたが、1661年スウェーデンではわずか10年しか続きませんでした。
今まで硬貨を使ってきていたのであれば、ただの紙片に同等の価値を見出すのは難しいですよね。
1694年にロンドンに設立されたイングランド銀行がスターリング・ポンド紙幣を発行は、今も使われています。
問題はあったものの少しずつ現在のお金の仕組みに落ち着いたようです。
お金について最も大切で理解するのが難しいことは「お金は人々がそれを信じているから存在している」ということです。
私たちは、紙幣や硬貨のような目に見えるものが現金だと思っていますが、本来お金には形はありません。
実際、ある国で使われている紙幣や硬貨全て集めて数えたとしても、その総額はとても少ないと言われています。
なぜなら、ほとんどのお金は銀行に預けられているからです。
銀行はお金の貸し借りで出た利息を受け取ることで利益を得るため、だいたいの現金を貸出に用いています。
そのため、銀行が何らかの理由で仕事を休止することになり、政府が間に入って手助けをしなければ、銀行に預けたお金はほとんど無くなってしまうそうです。
また、お金には決まった価値があると考えがちですが、100円で買えるものの値段は常に変化しています。
その例として、物の値段が上がっていくインフレーションと、物の値段が下がってお金の価値が上がるデフレーションなどが挙げられます。
お金はコントロールするのが難しいものなのです。
「いくらかかる?」
「どれくらいの価値?」
「他の人より多く稼いでる?」
今、私たちは何でもかんでもお金の面から考えるようになってしまっています。
売り買いできないものは価値がなく、人生で必要なのはできるだけたくさんのお金を持つことだ!
と考えてしまう人もいるかもしれません。
しかし、これは心身ともに豊かになっていると言えるのでしょうか。
皆さんはどう思いますか?
最後までご覧いただきありがとうございました。
お金や社会経済の成り立ちを知ることで、金融に対して親近感が湧いてきませんか?
このコラムが、誰かが金融を学ぶきっかけになれば嬉しいです。
参考図書
マーティン・ジェンキンス著/吉井一美訳/きたむらさとし絵『なるほど!お金のはなし』BL出版 2015.
https://www.blg.co.jp/blp/n_bl...
Let’s share with Us!
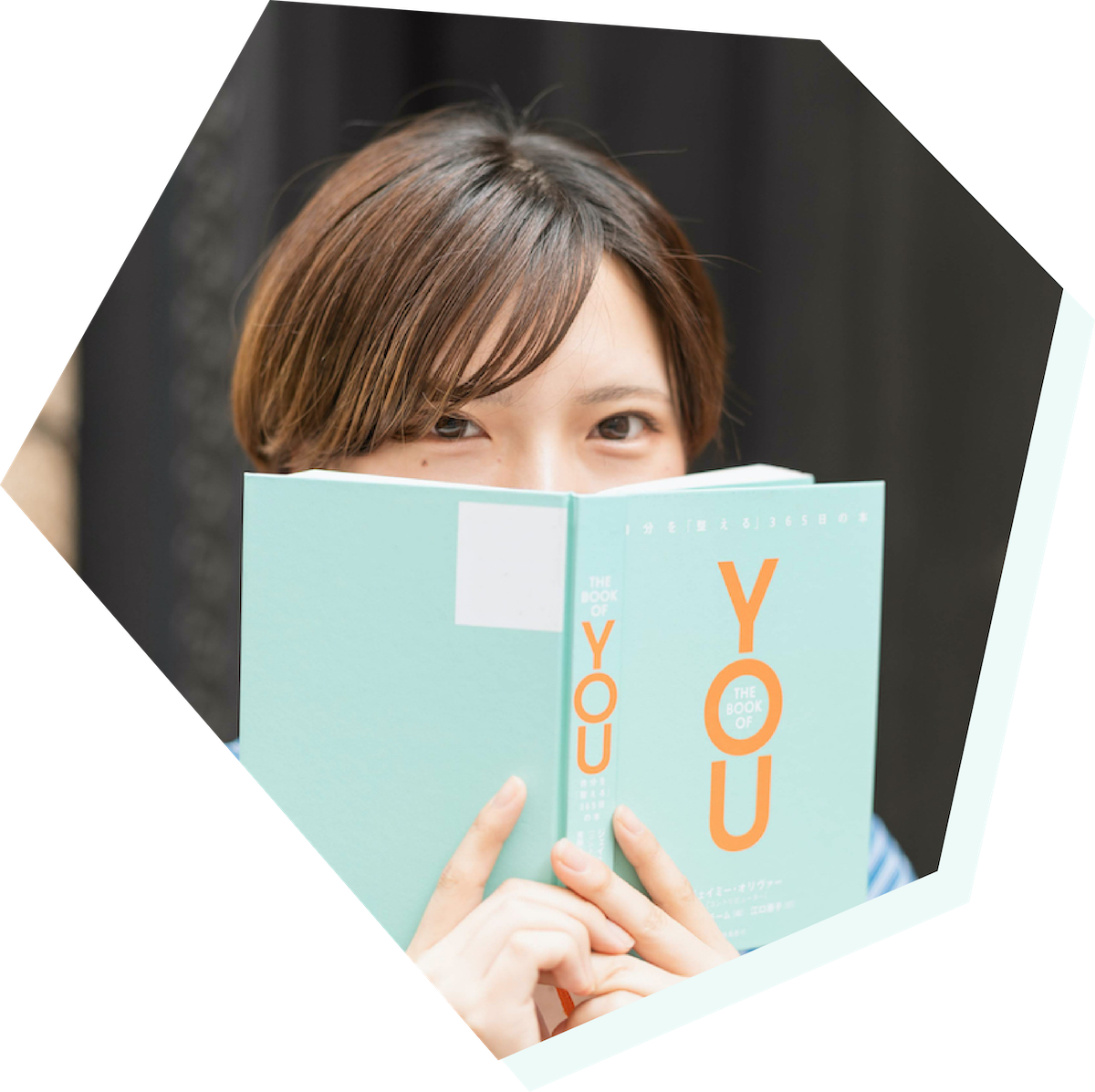
自分の感じていることを素直に表現しよう。
定期的にメルマガでアンケートをお送りします。アンケートに回答することで、みなさんの金融や経済に関する声を届けてください。コミュニティだけでなく社会にも貢献しましょう。

自分の体験や生活の工夫を発信しよう(女子会や記事で)
お金テーマ×あなたの得意なこと・好きなことをテーマに女子会や教室を主催したり、編集部に体験談を寄稿することができます。金融・経済だけでなく、日々の生活をちょっと豊かにする考え方や工夫などもお待ちしています。

オンラインコミュニティでつながって、語り合おう、支え合おう
オフィシャルメンバー限定コミュニティでは、メンバー同士がオープンに会話ができます。誰かが疑問に思ったことや寄せられた質問やモヤモヤ・お悩みはみんなで解決!マナーを守って参加してくださいね。

OMCでの活動に応じてソーシャルギフトをお届け。有意義に使おう。
活動の頑張りに応じて、時々「お礼(ソーシャルギフト)」をお届けいたします。コミュニティが活性化していくことで一人一人にパワーチャージできる仕組みです。(ソーシャルギフトはAmazonギフト等になります)
Special Contents
Coming soon!

金融のお役立ち情報
金融に関する情報を集めていると不安に思ったり、相談したいことってありますよね。そんな時に役に立つ金融機関さんが発信している情報をまとめてみました。
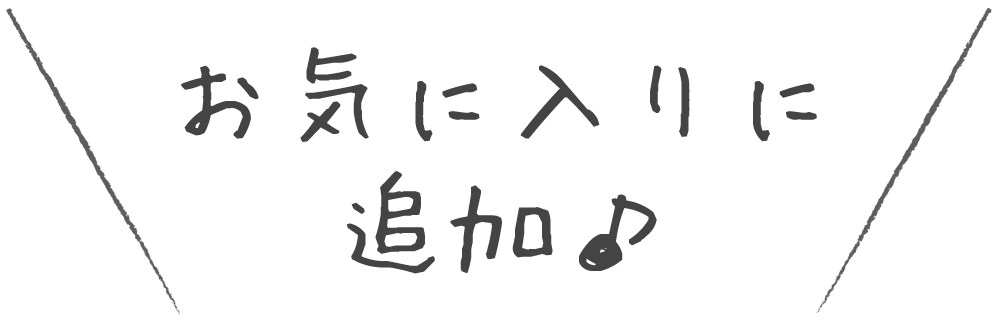
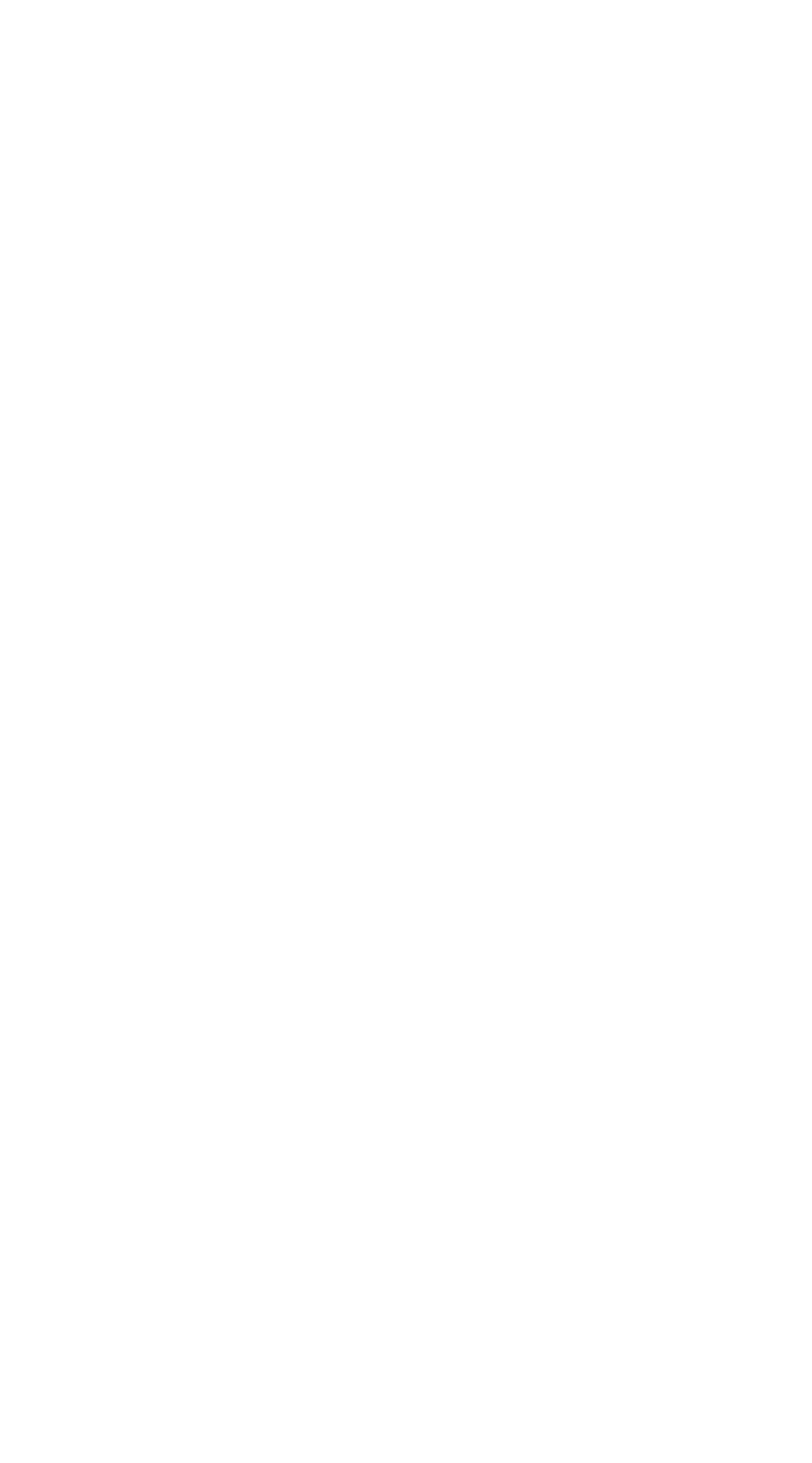
送信中です...。